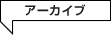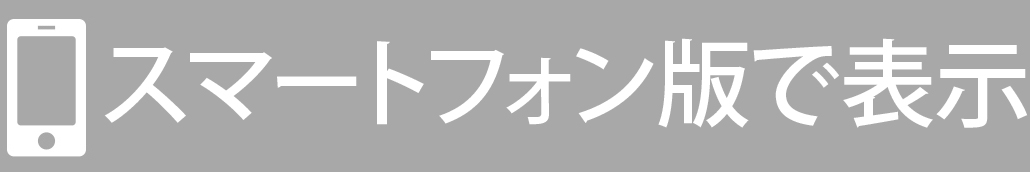HONZ記事
-
『評伝クリスチャン・ラッセン』なぜ日本で人気なのか
2024年4月19日まだ学生だった頃の話である。その日、山手線のある駅で待ちぼうけを食っていた。ふと周りをみるとギャラリーがある。ガラス張りで見通しがき…more
-
『異常殺人 科学捜査官が追い詰めたシリアルきらーたち』「黄金州の殺人鬼」を追い詰めたCSI捜査官の捜査記録
本書に記載されている調査によると、現在アメリカ国内で活動中の連続殺人犯の数は2000人ほどだという。その多くは孤立者でもなければ社会…more
-
『Mine! 私たちを支配する「所有」のルール』現代社会の所有概念とは?
「私のもの!」という感情が私たちの生活にどのような影響を及ぼすのか。本書を読むと、何気なく過ごしていた日常が全く異なって見える。「座…more
-
『私がしたことは殺人ですか?』25年の時を超え、もう一度「尊厳死」を問う
2024年3月5日、京都地裁はALS(筋萎縮性側索硬化症)の女性患者に関する嘱託殺人及び別の殺人罪に問われた医師、大久保愉一被告に懲…more
-
さようならマーシュ先生 ”残された時間” を大切にお過ごしください
2024年4月10日ヘンリー・マーシュ先生。会ったことのない著者は呼び捨てにするのが習わしだろう。しかし、マーシュ先生の処女作を読んだときから、先生とつ…more
-
『本屋のない人生なんて』本屋だからできることがある
近所に夜中まで開いている小さな本屋がある。開いているといっても、頑張って遅くまで営業しているという感じではない。店先に並べられた雑誌…more
-
あれから10年。『「笑っていいとも!」とその時代』が示す未来。
あれから10年です。 国民的人気番組だった『笑っていいとも!』が約32年間の歴史に幕を閉じた日から、きょう(2024年3月31日)で…more
-
「イノベーションは加速化する」なんてウソや! 『Invention and Innovation : 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』
2024年3月27日「やっぱり自分の考えが正しかったんや!」 思わずそう叫びたくなった。 多くはないが、大勢の意見と自分の考えが違っていることがある。気…more
-
『[完訳版]第二次世界大戦 1』英国式「カントリー・ジェントルマン」人生!
2024年3月22日国家がひとりの勇敢な人間によって救われることがある。ウィンストン・チャーチル(1874-1965)は第二次世界大戦中に英国首相となり…more
-
『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』は、笑って読めてタメになる最高の一冊だ!(← 自己肯定感マックスです)
2024年3月20日まいどお世話になっております、HONZレビュアーの仲野でございます。このたび、『仲野教授の この座右の銘が効く』という本を上梓いたし…more
-
『トヨタ 中国の怪物』トヨタの中国進出と創業家世襲に秘められた歴史
2024年3月19日一見関係のないものを掛け合わせると、思いもよらない新しいものが生まれることがある。本書は「中国現代史」と「トヨタ創業家の歴史」を組み…more
-
逆境を生き抜いた開拓者、かく語りき 『女性が科学の扉を開くとき』
2024年3月18日かつての米国科学界における女性に対する偏見と差別がここまですごかったのか。いまさら驚くとはお前の認識不足だろうと言われるかもしれない…more
-
『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』東日本大震災13年目にあの人を思い出す
2024年3月15日新聞や放送局といった組織に属する記者と、フリーランスのジャーナリストの立場は全く違っている。大手メディアを背中に負う取材陣は恵まれた…more









![『[完訳版]第二次世界大戦 1』英国式「カントリー・ジェントルマン」人生!](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/4622096315.09.LZZZZZZZ)