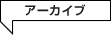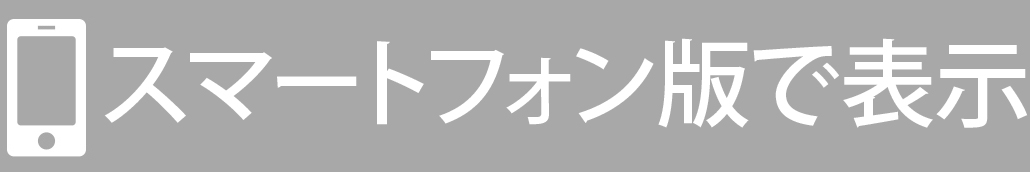みなさま、あけましておめでとうございます。
本年も相変わりませず、HONZをよろしくお願いいたします。
さて新年始まって、最初にお詫びから。
「12月の今月読む本」ですが、その2をUPするのをすっかり忘れてしまいました。
怒涛の年末進行のなか、気づいた時にはもう20日過ぎ。合宿の関係で、全員の3冊は揃っていましたので見送る事にいたしました。
楽しみにしていた方、本当に申し訳ありませんでした。
そして新年1回目の朝会になのに、欠席者は鈴木葉月、高村和久、久保洋介、栗下直也、仲野徹、鰐部祥平、野坂美帆と多数。彼らの「今月読む本」はその2に回します。
というわけで2014年のHONZ出発進行!
「お~いお茶」「マイルドセブン」「ポカリスエット」など時代が変わっても愛され続けている商品の、パッケージデザインの変遷をたどる一冊。
最近流行りのシェアハウスやシェアオフィスなどの設計について。密かにこういうものの経営を目論んでいるらしい。
ふーちゃん、またこんな本?と思うなかれ。なんと印象派の画家たちの肖像がイラストで描かれているという斬新さ。私のような絵画音痴にはちょうどいいかもしれない。「中野京子、絶賛」の帯が!
ハーバード大、マサチューセッツ工科大、スタンフォード大など、名門大学がインターネットで次々と講義の無料配信を始めた。日本では今後どうなっていくのか。
上の本の隣にあって思わず手に取った1冊だとか。大学の講義が無料になった場合、教育はどのように変わるのかを知りたい、と山本。
これは私がカブってしまった。遺伝子によっておこる病気や性別など、出生前にわかることでどんなことが起こるのか。大きな警鐘を鳴らす。
卒論製作中の刀根。この本はその一環で読んでいるらしい。
学生メンバー募集中。面接は村上が行います。われと思われる方は是非!
でた、厚い本!成毛眞も持ってきた飛行機好きにはたまらない一冊。
アメリカのサイエンスライターはどうやって記事を書いているのか。なりたい人と読みたい人のための本。
科学史上に輝くふたりの天才の生涯と大発見、時代背景を書簡から読み解く評伝。独の科学ジャーナリストによる労作。
かなり意気込んで持ち出した1冊が、すでに紹介された本であることを知り意気消沈する足立…
「テルマエ・ロマエ」の作者が語る、古今東西の魅力的な男たち。
「形こそは言葉なき対話の手段だ。そして無数の人同士が相互理解を深めるための基盤である」東大での講義録第3弾。
今観るべきドラマを書いた6人の脚本家を分析する。
1930から40年代に未来を予測して描かれたものが、どれくらい実現したのかの大図鑑。これは欲しい。
「類は友を呼ぶ」というけれど、友達の影響を私たちはどれだけ受けているのだろうか?
150年に及ぶ写真の歴史を前半120年と後半30年にわけて辿る。デジタル化は何を及ぼしたのか。
1937年、日本に講演旅行にやってきたボーア。見たもの感じたことを息子のハンスの手記から書き起こす。
書店で見たとき、誰が買うんだろうと思っていたのだけど、土屋が買ってました。世界中の暗号解読を読み解き、巻末には練習問題も。意外にもメンバーの人気が高く、購買欲をそそられていた。
磯田史学の結集ともいうべき論文集。だからといって難しいわけではなく、具体例が面白い。日本の歴史小説家は必読だと思う。
週末のサイトリニューアルに向けて奮闘中。正月休み返上で頑張ってくれてます。
『チューリングの大聖堂』を書いた著者と父親の天才物理学者との確執を描いた作品。世代間の断絶など、1960~70年代アメリカのさまざまな姿を浮かび上がる。
ひとことで言うと「不気味な人」だと内藤は言う。本書が出たときにamazonでジェフ・ベゾスの奥さんが星ひとつをつけたことでも有名。それにしてもamazonはどこまで大きくなるんだろう。
1999年に出た本の文庫化。それにしても内藤はよほど「高橋お伝」が気になるらしい。
もうすぐ『もっと面白い本』(岩波新書)発売です。
書体とか活字は面白い。それによって本の印象ががらりと変わってしまう。本書は編集者必読の書。
現代の歌舞伎評論の泰斗が語る「型」の本質と魅力。
フィルムアート社の101のアイデアシリーズはとても面白いのだが、この本は工学的なものに注目した1冊。理科系向き。
今年も栗下とのバトルが楽しみ。
清武の乱で有名になってしまったが、もとは素晴らしいジャーナリスト。『滅びの遺伝子』と合わせて読むと面白い、と成毛からのアドバイス。
軍隊がくれば地元が潤いインフラが整って人々が豊かになる、と言われていた時代があった。都市計画から考える。
明治の大合併が行われる前、町は7万存在していた。昭和、平成と大合併が行われる中、日本はどう変化したか。
坂口恭平が一種の天才であることは間違いない。『TOKYO 0円ハウス0円生活』から注目しているが、自らの躁うつ病を医学書院で語るとは思わなかった。
言語学の専門家、それも外国人から見た日本のおネエことば。そもそも、これは何なのか。年末年始のテレビを見ていて不思議だった疑問を解決してくれそうだ。
世界で2番目に売れているゲームだそうである。みんなの興味は一気に「じゃ、一番売れているのは?」調べてみたらゲームソフトを除くとどうやら「人生ゲーム」らしい。
さて、近々、サイトを一新してさらに読みやすくします。「マンガHONZ」に応募された方も多士済々で発表が楽しみ。今年さらにパワーアップしたHONZをよろしくお願いいたします。