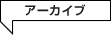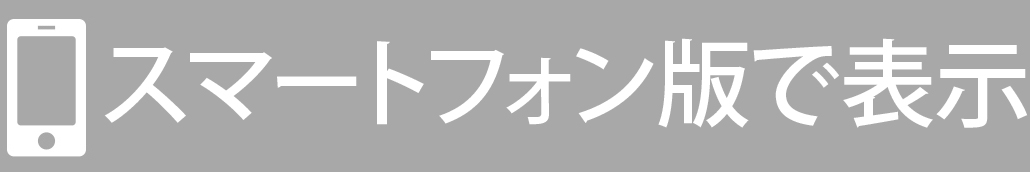社会
-
ノンフィクションの舞台を訪ねて 陸前高田への旅
みぞれまじりの空の下、車窓から鉛色の海が見えた。いかにもリアス式海岸らしい入江になっていて、風があるのか波が高い。「この先、津波浸水…more
-
『再生』加害者を赦せるか
読み終えたあとも、まだ消化できないものが残っている。こと読書では、これはマイナス評価ではない。たやすく消化できるものばかりが良い本と…more
-
『硫黄島上陸 友軍ハ地下ニ在リ』今も1万人の遺骨が見つからない。日本政府に遺骨収集への考え方を問う
2024年5月16日太平洋戦争末期、小笠原諸島の硫黄島でアメリカ軍と栗林忠道陸軍中将率いる日本軍の激戦があったことは、クリント・イーストウッド監督の映画…more
-
『異常殺人 科学捜査官が追い詰めたシリアルきらーたち』「黄金州の殺人鬼」を追い詰めたCSI捜査官の捜査記録
本書に記載されている調査によると、現在アメリカ国内で活動中の連続殺人犯の数は2000人ほどだという。その多くは孤立者でもなければ社会…more
-
『Mine! 私たちを支配する「所有」のルール』現代社会の所有概念とは?
「私のもの!」という感情が私たちの生活にどのような影響を及ぼすのか。本書を読むと、何気なく過ごしていた日常が全く異なって見える。「座…more
-
『私がしたことは殺人ですか?』25年の時を超え、もう一度「尊厳死」を問う
2024年3月5日、京都地裁はALS(筋萎縮性側索硬化症)の女性患者に関する嘱託殺人及び別の殺人罪に問われた医師、大久保愉一被告に懲…more
-
『本屋のない人生なんて』本屋だからできることがある
近所に夜中まで開いている小さな本屋がある。開いているといっても、頑張って遅くまで営業しているという感じではない。店先に並べられた雑誌…more
-
「イノベーションは加速化する」なんてウソや! 『Invention and Innovation : 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』
2024年3月27日「やっぱり自分の考えが正しかったんや!」 思わずそう叫びたくなった。 多くはないが、大勢の意見と自分の考えが違っていることがある。気…more
-
社会学って何?と思うあなたに 『戦後日本の社会意識論 ある社会学的想像力の系譜』をどうぞ。
社会学者、と聞いて、誰をイメージするでしょうか? 古市憲寿さん、岸政彦さん、宮台真司さん・・・。 世代などによって、かなり異なるかも…more
-
『モサド・ファイル2』イスラエルを影で守る「モサド・アマゾン」たち
前作『モサド・ファイル』でイスラエル建国以来、同国の「諜報機関モサド」が行ってきた秘密作戦の全貌を明らかにしたマイケル・バー=ゾウハ…more
-
『それでも私は介護の仕事を続けていく』追い詰められても立ち上がる施設利用者と介護者たち
12年前『驚きの介護民俗学』(医学書院)という本を書店で見つけた。著者の六車由実さんは『神、人を喰う』でサントリー学芸賞を受賞した民…more
-
『狼煙を見よ』東アジア反日武装戦線とは何だったのか
警視庁を担当する記者からの一報に驚いた。 「『東アジア反日武装戦線』のメンバー身柄確保との情報」 1974年から75年にかけて起きた…more
-
『セカンドキャリア 引退競走馬をめぐる旅』競馬業界のタブーに挑む衝撃のルポルタージュ
2023年の有馬記念を制したのは前年の日本ダービー馬「ドゥデュース」だった。騎乗の武豊に「千両役者ここにあり」とアナウンサーが叫ぶほ…more
-
『災害の記憶を解きほぐす』『異邦人のロンドン』記憶の風化を止めるためには…。
2023年12月16日記憶の風化を止めるには新しい世代に記憶を移植するしかない。誰かに継代されることで災害の防御にも繋がっていく。 『災害の記憶を解きほぐ…more