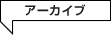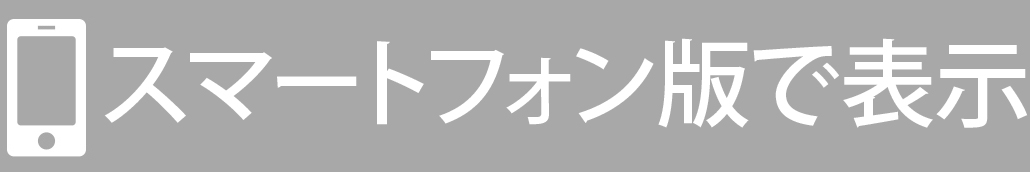澤畑 塁
-
『心の進化をさぐる──はじめての霊長類学』 言語と記憶のトレードオフ、そして「想像するちから」
2017年10月3日著者は次のような進化的シナリオを紡ぎ出す。かつて、ヒトとチンパンジーの共通祖先は、いまのチンパンジーにあるような瞬間記憶の能力を有し…more
-
『予期せぬ瞬間 医療の不完全さは乗り越えられるか』 医者と医療にまつわる不完全と不可解と不確実
2017年9月12日『死すべき定め』は、「死をどう迎え入れるか」というテーマに対して、円熟した文章で迫ったものである。他方、研修医時代に書かれた本書は、…more
-
『健康格差 不平等な世界への挑戦』 Fair society, healthy lives.
スコットランドのグラスゴーの話。その市のなかの、たった数キロしか離れていないふたつの地区は、驚くべき対照を見せている。一方のレンジー…more
-
『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』 進化認知学、そして「唯一無二の人間」という見方からの脱却
2017年8月30日フランス・ドゥ・ヴァールは、ベストセラー『チンパンジーの政治学』といった著書もある、世界的に著名な霊長類学者である。そんな彼が本書で…more
-
『世界からバナナがなくなるまえに 食糧危機に立ち向かう科学者たち』 ロペスのハチ、チョコレート・テロ、現代版ノアの箱舟
本書でおもしろいのは、その議論を展開するために、「食糧危機に立ち向かう科学者たち」の姿を描いている点だ。未来のためにいち早く世界各地…more
-
歴史的偉業を世界に知らしめよ 『ライト兄弟 イノベーション・マインドの力』
"ライト兄弟がなした最大の偉業といえば、もちろん「人類初の動力飛行」である。そして本書の前半部も、1903年12月17日にその偉業が…more
-
『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』 「言葉が分かるとはどういうことか」を人工知能から考える
2017年6月17日この新作で、著者はまた新たな挑戦を試みている。ひとつは、その舞台設定。今回の本も物語の形式をとっているが、登場するのは「働きたくない…more
-
自閉症は増えているのか? 『自閉症の世界 多様性に満ちた内面の真実』
2017年6月1日ひとつの「謎」から話を始めよう。1970年代まで、アメリカにおける自閉症の推定有病率は数千人に1人であった。ところが、1980年代以…more
-
『われらの子ども 米国における機会格差の拡大』 危機にあるアメリカン・ドリーム
2017年3月31日"アメリカン・ドリーム。それは、大志を抱く者が自らの実力ひとつでのしあがっていくサクセス・ストーリーである。しかしじつは、そんなアメ…more
-
細胞レベルから健康になる 『テロメア・エフェクト 健康長寿のための最強プログラム』
2017年3月2日「同じ年齢なのにどうしてこうも違うのか」と思うことが少なくない。たとえば同じ60歳でも、Aさんは背筋がピンとしていて、肌には張りがあ…more
-
『フンボルトの冒険 自然という<生命の網>の発明』 多事多難な探検と、そこから芽生えたアイデアの数々
偉大な探検家にして傑出した博物学者。壮年の文豪ゲーテに再び情熱の火を点し、その著書によってダーウィンをビーグル号乗船へと促した男。ジ…more
-
『脳はなぜ都合よく記憶するのか 記憶科学が教える脳と人間の不思議』 創造的能力の副産物としての記憶違い
2017年1月8日わたしたちの記憶はどうして移ろいやすいのか。また、記憶がときとして大きく歪められてしまうのは、いったいどうしてなのだろう。本書は、そ…more
-
『マイクロバイオームの世界 あなたの中と表面と周りにいる何兆もの微生物たち』 研究の全体像を見渡せる概論的読み物
2016年12月9日近年、わたしたちの体内や体表面に驚くほどの微生物がいることが明らかになってきた。人間の体にある細胞のうち、なんと90%が微生物のもの…more
-
「ビッグマック」を食べよう 『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』
2016年12月4日100,000,000,000,000。わたしたちひとりひとりの腸内にはそれだけの数の細菌がいるという。そうした細菌たちの集まりは「…more
-
『超予測力 不確実な時代の先を読む10カ条』 一番大事なのはものの考え方
著者のフィリップ・テトロックは、一般のボランティアを広く募集し、大規模な予測コンテストを継続的に行っている。そして、その結果として浮…more