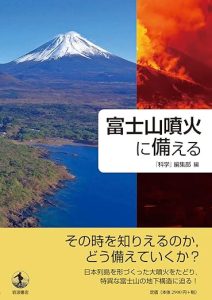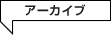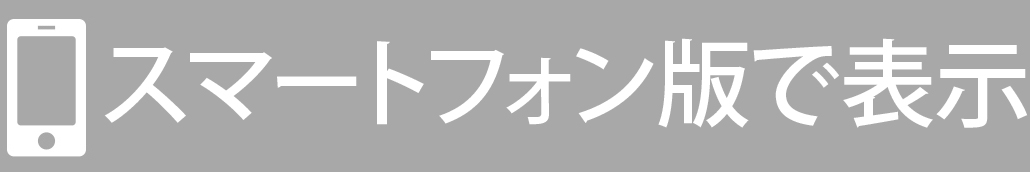生物・自然
-
『ライチョウ、翔んだ。』このままでは絶滅する…。難題を解決することはできるのか?
2024年6月21日2015年8月、衝撃的な写真が新聞に掲載された。北アルプスのライチョウがニホンザルに捕食されている姿が初めて撮られたのだ。ライチョウ…more
-
『地球規模の気象学』 地球の巨大な循環システムが天気を決める!
2024年5月28日昨年の夏は猛暑だったが、実は2023年は世界的にも気象観測史上で最も暑かったことがデータから裏付けられている。こうした現象を研究する…more
-
『首都直下 南海トラフ地震に備えよ』東日本大震災は「まだ終わっていない!」
2024年5月13日2024年の元日に能登半島地震が発生し、多くの犠牲者が出た。現在も復興作業が続けられている最中だが、その後も千葉県・房総半島沖で地震…more
-
『もしも世界からカラスが消えたら』『カワセミ都市トーキョー』”鳥ノンフィクションに外れなし!”
2024年5月2日鳥ノンフィクションに外れなし 長くノンフィクションを読んでいるからこそ、確信をもっていえる。私は鳥好きではないが、「鳥」が魅力的な生…more
-
『津波―暴威の歴史と防災の科学』国際語「Tunami」の歴史と減災を知る好著!
2024年4月22日「Tunami」は英語の辞書にも載っている数少ない日本語起源の国際語である。本書は津波に関する歴史的な逸話を、最先端の研究成果をもと…more
-
『世界から青空がなくなる日』 自然のコントロールをコントロールする
2024年3月12日著者のエリザベス・コルバートは、前著『6度目の大絶滅』(NHK出版)でピュリッツアー賞も受賞した実力派のライターである。そんな彼女が…more
-
『47都道府県・地質景観/ジオサイト百科』日本列島は美しい地質景観の宝庫だ!
2024年2月23日いま日本で「地学」がブームになっている。日本列島の地質は世界的に見てもユニークなものが多い。プレート境界で火山が集中し地震も活発な島…more
-
昆虫のいない世界、それはディストピア 『昆虫絶滅』
2024年1月27日『昆虫絶滅』、なんとも刺激的なタイトルだ。まずはプロローグで、「昆虫のいない世界」がいかなるディストピアであるかが描かれる。 昆虫が…more
-
『セカンドキャリア 引退競走馬をめぐる旅』競馬業界のタブーに挑む衝撃のルポルタージュ
2023年の有馬記念を制したのは前年の日本ダービー馬「ドゥデュース」だった。騎乗の武豊に「千両役者ここにあり」とアナウンサーが叫ぶほ…more
-
2023年のイチオシ本=関東大震災100周年を忘れるな! 『関東大震災がつくった東京』
2023年12月30日今年も日本各地で地震が頻発する1年だった。地球科学を専門とする私には、ある意味で予測されていることでもある。 というのは12年前の東…more
-
『八ヶ岳南麓から』山暮らしのリアル
2023年12月7日これまでたくさんの本やエッセイを書いてきた著者だが、意外にもプライベートな暮らしについては、ほとんど書いたことがないという。本書はこ…more
-
『富士山噴火に備える』「噴火スタンバイ状態」の富士山はどうなっているのか?
2023年11月14日万葉集が編まれた頃、富士山の頂上から噴気がなびいていた。つまり、当時の人々は富士山が「生きている」ことを知っていたのである。その後は…more
-
『宗教の起源──私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』 ダンバー数、エンドルフィン、共同体の結束
ここで非常に興味深いのが、議論の出発点がダンバー数となることである。冒頭で述べたように、安定的な社会的関係を維持できるヒトの集団サイ…more
-
『世界がわかる資源の話』世界の地政学のベースに「資源」がある!
2023年9月11日資源は私たちの生活に欠かせないものである。エネルギーや有用な元素を供給してくれる鉱産資源は、46億年に及ぶ地球の歴史のなかで培われて…more
-
『ロバのスーコと旅をする』相棒ありの放浪
うんと幼い頃、ロバのパン屋さんという行商があった。記憶は遠く、かすかに覚えているのはロバの瞳だ。大きな目の中の全部が黒くてまつ毛が長…more