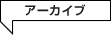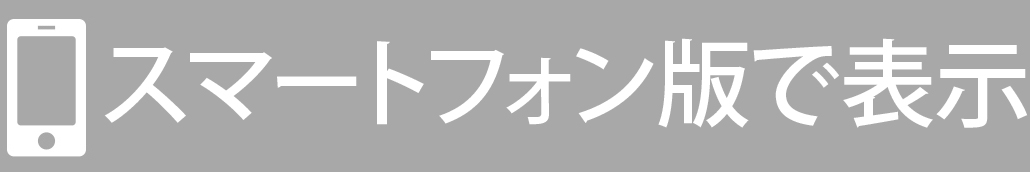HONZメンバーが選ぶ、今年最高の一冊。ようやく出揃いました! いや厳密に言うと、まだ出揃っておりません。まず最初に、少しだけ業務連絡をさせてください。
「成毛代表、原稿お待ちしております。何とか年内のうちに、よろしくお願いします!」
さて、世間では「平成最後」のキーワードが飛び交っておりますが、こちらのラインナップは、「平成最後」とは無関係なものばかり。そう我々は、平成最後だからといって本を読むワケではないですし、元号が変わったからといって本を読むワケでもない。ただ面白ければ、それでいいんです。
そんな珠玉のラインナップを、今回は原稿が届いた順にご紹介いたします。締切より前の日に届いた人たち、締切日当日に駆け込みで送ってきた人たち、そして締切を過ぎた後に送ってきた人たち。まぁ色んなタイプの人がいてホント面白いです。編集長冥利に尽きます。
それでは、どうぞ!
堀内 勉 今年最も「反響の大きかった」一冊
HONZで書評をアップするときに、読者の反響を気にしていたら好きなことは書けないが、それでも結果的にどれくらいの「いいね!」がついたかとかは気になるものである。だから、書評の反響は、事前になんとなく予想(予感?)はするのだが、自分でもビックリするくらい反響が大きい場合がある(逆もまた真なりだが・・・。)
この『ティール組織』は固いビジネス書だから、大した反響は期待していなかったのだが、実際の反響の大きさには、正直かなり驚かされた。ティール組織というのは、従来の軍隊式でもフラット型でもない、セルフマネジメントを基本とした常に変化する目的を追求し続ける進化型モデルであり、日本人のようなルール大好き人間の国とはとても馴染まないだろうと思っていたからである。
本書を読んで最後に気付かされたのは、我が国においても試行錯誤の「働き方改革」なるものが進められているが、本当に必要なのはそうした時短とかホームオフィスとかの話だけではなく、その前提になる組織自体の改革(本書の原題:”Reinventing Organizations”)であり、もっと言えば、一人一人の生き方の変革だということである。それだけ、今の世の中の変化のスピードとパラダイムシフトは急であり、皆、そのことに薄々気がついているのだと思う。 ※レビューはこちら
仲野 徹 今年最も「怖くてしかたなかった」一冊
怨念とか幽霊とかの存在を信じているかと言われると、Noと断言できる。では怨念や幽霊が怖くないかと言われると、そうでもない。事故物件-前の住人が自殺したり、殺されたり、孤独死したり、事故にあったりした不動産物件-はどうだと聞かれると、微妙である。たぶん、大丈夫だという気がする。いや、正しくは、気がしていた、である。
この本を読んだら、むちゃくちゃ怖くなってしまったのだ。とんでもない出来事が偶然に重なる、ということがありえることはよくわかっている。それでも、「前の住人も前の前の住人も自殺している部屋」とか「二年に一回死ぬ部屋」に住む気がするかといわれると、絶対イヤだ。
そんな物件が延々と淡々と紹介されている。作り話ではない。何なんですかそれはと言いたくなる「事故物件住みます芸人」の松原タニシが実際に経験して書いているのだ。まぁ、タニシさんは生きてるんだから、たとえ住んでも命を落とすようなことはないようだ。
この本、あまりに怖くて、手元に置いておくと悪いことがおこりそうな気がしてきた。で、半分くらい読んだところでHONZの朝会に持参して置いてきた。持って帰った誰かが怖い目にあっていないか、ちょっと心配。
澤畑 塁 今年最も「家族と一緒に笑った」一冊
3歳になった息子がわが家を明るくしてくれている。誰に似たのか、四六時中おしゃべりをしていて、家族にいろいろな話題を提供してくれる。そんななかで、みんながとりわけ愉快な気持ちになるのは、息子がおかしな「言い間違い」をしたときだ。
家のなかに蚊が入ってしまったときのこと。息子は一生懸命になってこう訴える。「カガガ イルヨ。カガガ イル!」。妻とわたしが必死に笑いを堪えながら、「あれは『カガ』じゃなくて『カ』でしょ」と諭すものの、息子の「カガ」はなかなか直らない。それを見て3つ年上の娘は笑い転げているが、いやいや、あなただって当時は同じ間違いをしていたのだから。
そんなこともあって、昨年にヒットした本書を手に取ってみた。本書は、子どもたちの発話を手掛かりとしながら、人がどのようにことばを習得するかを考えていくもの。そうした本なので、上記のような言い間違いの例も数多くとりあげられているし、それらがなぜ生じるのかも説明されている。なお、「カガガ イル」は、「チガガ デタ」(血が出た、の意)などと同様、1拍(1文字)の語にもっぱら見られる現象とのこと。たしかにうちの子どもも「チガガ デタ」と言っていたなあ、と得心。
ところで、わが家の最大のミステリーは、つい最近まで娘が「西松屋」を「ニシマツヤマ」と言い間違えていたこと。「なんか『山本山』みたいじゃない?」、「途中で『松山』に引き寄せられちゃうのかな(妻の実家が松山にあるので)」などと語りあうのも楽しい。家族で回し読みしたい1冊でもある。
新井 文月 今年最も「制作の臨場感を味わえた」一冊
著者は現代アーティストの小松美羽。12月、三越伊勢丹にて開催された展示会では売上額3億円を突破した。容姿端麗な風貌とは対照的に、生み出されるタッチは豪快だ。狛犬などモチーフの作品は、目を見開き妖怪のようでもある。
現代アートは、村上隆が『芸術闘争論』をはじめ口酸っぱく論じるように、欧米アートルールには不文律が存在する。「死」をテーマとし、サメを輪切り&ホルマリン浸けするダミアン・ハーストのように、生き様を含めコンテクストを構築するのが定石だ。
しかし著者からは、それらを感じない。ぐちゃぐちゃな構図であっても、激しく跳ねた筆あとや血のような赤は観る人の視線が各所に移動させやすく目が離せない。これは天然型のゴッホに近いかもしれない。作品は妬み・嫉妬・競争心など私達の感情における負の面が強調され、引きずり出されるような感覚をも受ける。
本書では、段ボール箱を机に制作した苦労時代や、大きなプレッシャーからハート型のハゲができるエピソードなども描かれている。生きづらさや不条理も包括し、自分の内面と対話し泥臭く絵に置き換えてきた。制作の臨場感あふれる一冊だ。 ※レビューはこちら
東 えりか 今年最も「一家に一冊必携だと思った」一冊
目の前で階段を滑り落ちた人を見た。骨折したのか挫いただけかわからないが、呻いている。「大丈夫ですか?」と声をかけることしかできない自分。救命救急の指導は受けたことがあっても、それは心筋梗塞や脳溢血などのときで、怪我の手当ては何も知らないと気付いた。
世界的なテロが続き天災も毎年起きている。いつ巻き込まれるかわからない。海外なら銃で撃たれることだって想定できる。いつでも医療関係者がそばにいるわけではない。そんなときどうしたらいいのか。
本書は超リアルな写真とともに、怪我の程度を判断し、どのように手当てをしたらいいかを懇切丁寧に教えてくれる。特に怪我の部位によっての手当ての仕方は知らないことばかり。迷彩服を着ているのが可愛い女性だけというのはどうかしら?とも思うけど、誰でもできることなのだとも思える。
著者・監修者は陸上自衛隊富士学校普通科部と衛生学校にて研究員を務める。現代の戦傷医療に関するスペシャリスト。
村上 浩 今年最も「本の世界に入り込んだ」一冊
ポーランド総督府総督としてユダヤ人虐殺を進めたハンス・フランク、国家による文民に対しての残虐行為に対処するために「人道に対する罪」を提案したハーシュ・ラウターパクト、ギリシア語のジェノス(部族もしくは人種)とラテン語のサイド(殺人)を組み合わせて「ジェノサイド」という言葉をつくったラファエル・レムキン。
3人の人生が戦禍のヨーロッパで複雑に絡み合いながら、ニュルンベルク裁判で遂には合流する過程がドラマチックに描き出されている。
偶然の連なりがいつしか必然となり、歴史の謎が解き明かされていく展開は読者を本の世界に浸からせ、600ページに迫る大部を一気に読み通させる力を持っている。
人類が経験した最も大きな悲劇に対して法律家たち、そして世界がどのように向き合ったのか、どのような世界を作り出そうと願ったのか、遠くはなれた時代・地域に生きた人々の思いをリアルに感じさせてくれる一冊だ。 ※レビューはこちら
古幡 瑞穂 今年最も「魂を揺さぶられた」一冊
4月に劇団四季の『ノートルダムの鐘』を観て心を揺さぶられすぎたのか、あの衝撃を超える感動になかなか出会えず珍しく今年の1冊に悩む年だった。そんな中で出会ったのが『童の神』だ。時は平安時代。「童」と聞いたら何かピュアな、尊いものを想像するのだが実はこの時代の「童」は京人から差別され虐げられる存在。その中でも異国の母親を持つ主人公の桜暁丸はその姿形(今の時代では絶対ものすごいイケメンよ)からさらなる差別の対象として描かれている。
物語を通じて語られるのは長きにわたる朝廷と反乱軍の戦いなのだが、主人公の口から発せられる「同じ血の色を持つのに、なぜ自分たちが差別されねばならないのか」という叫びがずっと胸をえぐり続ける。
『ノートルダムの鐘』の終盤に「some day」という歌がある。
いつか 人がみんな 賢くなる時が来る ~中略~ いつか 人がみんな平等に暮らせるそんな 明るい未来が必ず来ると祈ろう。
この曲が桜暁丸の叫びに重なって、本を読んでいる間中アタマの中から離れなかった。心に最も刺さった芝居も小説も同じテーマだった、というわけ。
『童の神』は直木賞にもノミネートされ、注目度上昇中。ぜひ年末年始の1冊に手にとってみていただきたい。
鰐部 祥平 今年最も「大きく、高価で、興奮した」一冊
はっきりいって、完全に自分の趣味嗜好に走った選書である。今年購入した本の中で一番大きく、一番高価で、そして一番興奮した一冊である。それが、この『武器の歴史大図鑑』だ。素人採寸で縦36センチ、横26センチ、重さ2.2キロ。お値段1万2600円也。
けっして万人受けする様な本ではない。しかし、イギリスの戦史研究家の権威であるリチャード・ホームズが監修し英王立武器博物館の全面協力の下に作られた本書は全編オールカラーの写真で古代から現代までの武器と防具を網羅した大著である。この手のものが好物の人にとっては垂涎滴る一冊となっている。
武器は当然ながら戦争で使用される兵器である。しかしながら、武器の役割はそれのみに終わるものではない。時に武器を帯びる人の地位や財力を象徴するための小道具であり、ファッションの一部ですらあった。日本刀やヨーロッパのレイピアなどはその際たるもので、とにかく造り込みが精緻で美しい。
また武器のあり方は国家の進化の過程とも大きく関係がある。たとえば16世紀から17世紀にはヨーロッパで火器が普及し、従来の血統に依拠した戦士集団が弱体化し高度な訓練を受けた軍事エリートが台頭。国家の力も強大化し、さらに兵器が強力になっていく。本書でもその進化の過程を余すことなく見ることができる。
さらに、日本刀の異質さにも気づける。同時代のヨーロッパ、アジアの刀剣の刀身のほとんどが錆付き痛んでいるのに対し、日本刀のそれは、最近作られたかのように美しいのだ。刀剣の刀身を何世紀にもわたり美しく保つという価値観は日本のみに根付いた特殊な価値観であることが伺える。
内藤 順 今年最も「裏切らなかった」一冊
今年HONZ内で最も盛り上がったことと言えば、インド映画『バーフバリ 王の凱旋』の話題に尽きるだろう。映像良し、音楽良し、ストーリー良しのこの映画だが、荒唐無稽と称されることもある虚構感と現実世界とを見事につないでくれるのは、まぎれもなく俳優たちの筋肉である。
今やNetflixでいつでも見られることが出来るようになってしまったため、視聴回数も優に30回を超えてしまったが、ただ筋肉美を讃えるためだけに鑑賞するというのも一興ではないだろうか。そんな時、片手に持っておきたいのが本書『ボディビルのかけ声辞典』だ。
ボディビルコンテストにおいて、積み重ねてきた努力への称賛がかけ声となる現象は以前から見られたものだが、最近ではその褒め方も多種多様になり、もはや大喜利の様相を呈しているという。本書は、そんなユニークなかけ声ばかりを、まとめあげた一冊である。
「肩メロン」「二頭がチョモランマ」「腹筋板チョコ」「背中に鬼の顔」
そんな秀逸な掛け声の数々を知れば、画面の向こう側のバーフバリやバラーラデーヴァにも同様の掛け声を発せずにはいられなくなってしまうことだろう。

まさにバーフバリのために作られたかのような一冊ではあるが、ボディビル大会の新たな楽しみ方を知る一冊としても期待を裏切らない。そう、やはり筋肉は裏切らないのだ。
山本 尚毅 今年最も「脳内でリピートされた」一冊
2018年は、中国で恐ろしく話題になっていた信用スコアをウォッチしようと年初に決めていた。本書もその一環で迷わず購入した。そして、一つの原則に心奪われてしまった。その名は
「カリフォルニアロールの原則」。
なんともチープで、信用スコアと恐ろしく関係のなさそうな名前、だけど、一度聞いたら忘れられない。私の人生においてまったく重要な食物でなかったカリフォルニアロールが、どれだけ脳内でリピート再生されたことか。
なぜ、カリフォルニアロールは海苔が外に巻いていないのか
なぜ、カリフォルニアロールにはアボガトが入っているのか
なぜ、カリフォルニアロールは生の魚介を使っていないのか
従来の寿司との違いに隠された秘密は、新しいものを信頼してもらうためには、はじめてなのに見慣れたものにする必要がある、というシンプルな教訓だ。寿司という未知のものをアメリカに根付かせるための一歩目だった。
あ、全体はまったく寿司の本ではなく、カリフォルニアロールの原則は2ページほど、、、残りの372ページもおすすめです!
田中 大輔 今年最も「人生ってタイミングが全てよねと思った」一冊
今年最も刺激的だったノンフィクションは間違いなく『ノモレ』だった。ただそれは他の誰かが紹介していると思うので、私は今年最も面白かったビジネス書を紹介する。『When完璧なタイミングを科学する』だ。
HOW TOよりWHEN TO、どのようにやるかよりも、いつやるかのほうが重要だということを紹介した本だ。HOW TOの本は世の中にあふれているが、WHEN TOの本は世界初なのではないだろうか。
物事にはやるのに適したタイミングというものがある。人間の認知能力は1日で大きな変動があるからだ。しかもこの変動の幅は大きく、最高の時と最低の時のパフォーマンスは、素面と飲酒時の変化に匹敵するという。医療現場においては、検査での見落としや、術後48時間で死亡する患者の数など、午前と比べると午後のほうが圧倒的に多いという。手術や検査を受けるなら絶対に午前にしてもらいたいものだ。
開始、終了、その間。どんなものにも適したタイミングがある。2018年が終わり、まもなく平成も終わる。そして2019年には新しい時代が幕を開ける。そういった区切りのタイミングはなにか新しいことを始めるのにちょうどいい。これを機に何かを始めてみてはいかが?まずはこの本から始めてもよいかも。
西野 智紀 今年最も「思い出深い」一冊
日付を見たら、この本のレビューが載ったのは今年の1月3日だった。年末年始という、日本の伝統が意識されやすい時期だったためか、掲載後TwitterやFacebookを中心に凄まじい勢いで拡散され、Amazonは在庫切れが続き、「バズる」とはこういうものかとびっくりしっぱなしであった。本書の担当編集者によれば、ネット上だけでなく、都内の大型書店では完売し、追加注文が相次いだそうで、驚きを通り越してちょっと恐怖感すら覚えた。
いろんな面白い経験ができた年頭だったが、今年は全般的にあまり本が読めなかった。綱渡り生活が続いて、読書に向かう体力がほとんどなかったからだ。正直思い返したくもないので、年の瀬の今、ようやく一区切りつけて安心していると言うだけにとどめておく。
そんな、自己肯定感の低い(もとよりそんなに高くないが)一年であったものの、自分の書いたものが大きく影響を与えた体験は、励みであり支えとなった。つくづく自分は本に助けられてきた人生だなあと思わずにはいられない。
個人的な話ばかりになってしまったが、本書は伝統というものに息苦しさを感じる人にはもってこいの一冊だ。読んだ人の心のモヤモヤが少しでも晴れるのならば、幸甚の至りである。
アーヤ藍 今年最も「長い時間を共にした」一冊
マーシャル諸島共和国。そこはかつて日本が30年にわたって委任統治していた場所。アジア太平洋戦争では、約2万人の日本兵が主に飢えが原因で命を落とした。現在も多くの戦跡が残り、日本語に由来する言葉や日本風の名前も多く残っている。そんな深い繋がりがあるにも関わらず、日本ではほとんど知られていない。
この地を約10年前に初めて訪れ、両国の”過去と現在”をより多くの日本人に知って欲しいと願い続けてきた一人の女性が、今年ドキュメンタリー映画『タリナイ』と本『マーシャル、父の戦場』を完成させた。
何を隠そう、私はこの映画の宣伝をノリと勢いで手伝い始めたのだが、当初2週間のみの上映予定が、幸いロングランとなり、私の2018年後半は、思いがけずマーシャルで占められる日々となった。
本書は同地で失命した日本兵の日記を、赤外線などを用いて読解した全文が掲載されているほか、そこに奇跡のような運命のような縁で関わった15人の寄稿文が纏められている。”遠い”存在であるマーシャルを立体的に捉えられたほか、「日記」というものの存在意義、歴史を受け継ぐ方策や、映画と書籍の表現方法の違いなど、様々なことを考えさせられた一冊でもある。
仲尾 夏樹 今年最も「女友達に勧めまくった」一冊
平成が終わるこの年の瀬に、最も刺さったのは70年代のベストセラーでした。小難しいジェンダー論を展開するつもりはありません。本書にはただ、おいしいものを作って食べることは、人類にとって普遍的な価値があると書かれています。
すぐれた料理人は「聡明」です。例えば、献立を考え、調理をするには「果敢な決断と実行」、「大胆で柔軟な発想力」が求められます。また、経済的かつ、バランスの良い食事を作るには「鋭い洞察力」と「明晰な頭脳」が必要です。
普段料理はしない人も、本書を読めば、きっと台所に立ちたくなるでしょう。料理は食いしんぼうの恋人を持つことに始まる、とはまさにその通り。恋人に限らず、家族や友人でも、何をするにしたって、それを喜んでくれる人がいるからこそ、努力のしがいがあるのです。
本書には、優雅なパーティーの開き方や、世界中を食べ歩いて集めたレシピなど、聡明な料理人になるための情報が載っています。年末年始、親しい人との集まりにぜひ活用してください。
久保 洋介 今年最も「冬の気候を考えさせられた」一冊
「今年は夏が猛暑だったので冬は寒くなるはずだ」という迷信めいた予想もどこふく風で、今のところ本州を中心に例年以上の暖冬が続いている。今年は偏西風が本州付近で北に蛇行しており、北からの寒気の流れ込みが弱まっていることが主な原因だ。
冬が寒いかどうかはビジネスマンにとっては一番の飯の種となる。寒ければ暖房需要が高まるし、ホットドリンクやマスクなどの特需が見込める。色々な業界にとって、冬が寒いか温かいかをいち早く正確に把握することがビジネスでの成功につながるのだ。
冬の気象予想には巨額のマネーがこの予測に費やされており、各企業や行政機関はこぞって暖冬か寒波到来かを予測しあっている。その昔は「カマキリの産卵場所が高ければ冬の積雪量は多いはず」という迷信めいた予測もされていたが、今ではジオサイエンスが主流で、衛星を飛ばして北極の氷の大きさを調べることで寒波の流れを予想している。
地球科学を理解しているか否かで商売の勝ち負けが大きく左右される時代だ。年末年始にゆっくりする時こそじっくり地球科学の本を読んで、来たるべき大寒波か暖冬に備えたい。 ※レビューはこちら
冬木 糸一 今年最も「ぶっ飛んでいると思った」一冊
今年もたくさんノンフィクションを読んできたが、中でも一番ぶっ飛んでいると思ったのがロビン・ハンソン『全脳エミュレーションの時代:人工超知能EMが支配する世界の全貌』だ。脳をスキャンしてから、脳細胞の特徴や結合をそのままモデルとして構築・再現した存在のことを本書では「全脳エミュレーション」と呼んでいる。
本書でははたしてそんなことが科学的なプロセスとしてできるかどうかはいったんスキップし、はたしてそんな存在が生まれたら、未来は、友人関係は、生殖活動は、存在の基盤となるハードウェアはどう管理されているのだろうか──といったことを全30章に渡って語り尽くしていく。
おもしろいのは、それが単なるサイエンス・フィクション的な妄想ではなく、著者自身は『本書の推測は十分な根拠に基づいたもので、単なる憶測レベルとはかけ離れている。』と自画自賛している点だ。
確かに物凄く細かく考察していて、読みながらただただこいつは頭がおかしいぜ! と驚かずにはいられないほどなのだが──果たして本当に単なる憶測レベルとかけ離れているかどうかは読んで確かめてみてもらいたいところである。
首藤 淳哉 今年最も「クールな主人公と出会えた」一冊
今年ほど「移民」という言葉がクローズアップされた年はなかった。政府はいまだにこの言葉を使うことを避けているが、日本で暮らす外国人が増加の一途を辿り、すでに独自の文化や習慣を持ったコミュニティが各地に生まれていることは周知の事実だ。いまや移民はぼくたちの隣人である。
ミステリ界に彗星のごとく現れた『IQ』は、そんな時代の空気と見事にシンクロした一冊だった。ロサンゼルスに住む黒人青年、通称“IQ”ことアイゼイア・クィンターベイの活躍を描いたこの小説は、新しい“シャーロック・ホームズ”の誕生と話題を呼び、ミステリ新人賞を総なめにした。しなやかな知性と熱いハートで黒人社会の過酷な現実を生き抜いていく主人公が最高にクールだ。
著者のジョー・イデは貧しい日系アメリカ人の両親のもとに生まれ、ロスの中でも犯罪が多いことで知られる黒人街で育ったという(政治学者のフランシス・フクヤマは従兄にあたる)。日系人の著者が黒人コミュニティを見事に描く。これからは著者のような複雑な背景を持った人材が活躍することが日本でも当たり前になるだろう。そんな間近に迫った未来も予感させる一冊だった。
麻木 久仁子 今年最も「充実した時間ををくれた」一冊
最近HONZに「著者自画自賛」というコーナーが新設され、第一弾としてHONZメンバー仲野徹が自著『(あまり)病気をしない暮らし』について語っていました。「読んだやつはみな大絶賛だぜ、こんなすごい本はないぜ(大意)」と文字通り自画自賛。確かに売れているらしいです。
売れているといえばHONZ代表・成毛真も今年は『amazon世界最先端の戦略がわかる』がバカ売れしています。二人とも自己肯定感が強固、ってとこが似てます。いつも羨ましく憧れて眺めている二人です。
さて、自著なら私にもあるのです。幼い頃から自己肯定感が薄く、コンプレックスに振り回されてきた私はなかなか口に出せないのですが、結構頑張って作ったいい本なんです。『生命力を足すレシピ』という本です。8年前に脳梗塞、6年前に乳がんを患い、幸い早期発見で事なきを得たものの、健康管理の大切さに目覚めた麻木が、長続きする食養生を探し求めて『薬膳』に巡り会い、日常の食卓に薬膳を取り入れるべくレシピをご紹介する本です。
「薬膳」というとなにか漢方薬とか入ってるの?という印象ですが、実際には「季節や体調、体質にあったものを食べる」というのが基本です。珍しい食材を使わなくともスーパーで売っている食材で作る事ができるのが日常の薬膳です。ハンバーグ、餃子、肉じゃが、カレー、野菜炒めetcといった極々日常のメニューも、ほんの一工夫で季節や体調にあった「薬膳」になるという、毎日できる簡単薬膳を提案しています。
すでにこの本を手に取ってくださった方からは「薬膳のイメージが変わった!」「簡単に作れて美味しかった!」「どれも体に良さそう!」とのお声をいただいております。何度も試作して、できるだけシンプルで美味しいレシピを目指しました。撮影時は3日間、料理を作りまくりでしたが、いやあ楽しかったです。
この本は私に充実した時間をくれました。皆様におかれましても、お役に立つ本になればいいなと密かに思っております所でございます。よろしくお願いいたしまする。
刀根 明日香 今年最も「世界をぎゅっと凝縮した」一冊
「人間が赤ちゃんから大人になるのと同じで、時代も急に現代になったわけではない。積み重ねられた歴史を学んで、僕たちは立派な時代をつくれるのではないか。」出口治明さんの歴史の本はどこまでも分かりやすく、面白い。学生から大人まで、幅広い世代が「勉強したい」と思ったとき、その欲求を叶えてくれる、世界史教科書ナンバーワンだと思う。
私は物知りでもないし、特別な趣味もないが、読書はその平凡な人生に彩りを与えてくれるから好きだ。知って嬉しい、楽しい、こんな人に会ってみたいなど、少しずつ、自分のなかを「あれやりたい、これやりたい」で満たしてくれる、大切な習慣だ。仕事でうまくいかなくても、失恋しても、自分を立て直すための、大切な大切な自分の軸となっている。
出口さんの語る歴史を学ぶのは、等身大の自分を愛することに繋がるように感じる。等身大の自分が楽しめる本というのは、案外少ない。何かに追い立てられたり、少し背伸びして興味の幅を広げる挑戦をしたり。それらも素敵だが、純粋に好奇心を満たすために読みたくなる本、それが出口さんの本だと思う。過去にもたくさん素敵な歴史書はあるが、出口さんの本は万人に長く愛される本になるだろう。
栗下 直也 今年最も「私に残酷な現実を突きつけた」一冊
HONZに加入して以降、献本を頂く機会が増えた。スポーツやら事件モノやら男の欲望に関するモノが多い。編集者もバカではないので、私に『ホモ・デウス』は送ってこない。
そんな中、編集者であるHONZメンバーの足立真穂から、「担当の人から是非読んで貰いたいという本を預かりました。何か心配されているのかもw」のような連絡がきた。タイトルは『没イチ』。テレビでも取り上げられていたようだが、当時の私は読み方すら怪しかった。まあ、ボツイチとしか読みようがないんだけれども。
ググるとパートナーが没し、一人になった状態とある。ネットを見る限りアラフィフやシニアが多く、「え!俺はまだ、38歳だぞ、担当者!フレディ・マーキュリーも45歳まで生きているのに」と思ったものの、考えてみれば、アラフォーなんて、いつ、自分やパートナーがぶっ倒れてもおかしくない。事故にあうこともある。
肯きながら読んだが、モヤモヤも隠しきれない。そうなのだ。途中で気づいたのだが、私の場合、パートナーが先に没する可能性よりも、逃げられる可能性が圧倒的に高い。本書は没イチの心配の前に心配すべきことがある現実を突きつけてくれた秀作だ。
吉村 博光 今年最も「ミームが縁をつないだ」一冊
個人的な今年のニュースといえば、企画した「AI書店員ミームさん」が想像以上に波紋を広げたことだ。ミームさんはAIがお客様の表情にあわせて本を選ぶ仕組みだが、多くのメディアに出演し、国内外のイベントにも多数招待された。先日は「東京読書サミット」で本好きの方々に遊んでいただいた。(記事はこちら )
今回ご紹介する『インフォーメーション 情報技術の人類史』は、その際にお会いしたスマートニュースの藤村さんが、以前雑誌のインタビューでお薦めしていた本だ。
記事を読んで、早速、買って読んでみた。なんと「ミーム」についても書かれているではないか。運命を感じつつ、大変面白く読んだ。500ページを超える大作だが、私は(いつもそうするように)理解できないところを、バンバン飛ばしながら読んだ。文系の私に理解できるところだけでも、十分元はとれた。アフリカの太鼓(トーキングドラム)による情報伝達から、近年の情報通信に至るまで、その内容はエキサイティング!の一語。読んでからしばらくは、情報技術の今後を想像しながら過ごした。今もなおその余韻に浸っている。
塩田 春香 今年最も「小から大へ、振れ幅が大きかった」一冊
細菌は目に見えないほど小さいが、地球上の総量の見積もりは約520億~2700億t。人間の総体重よりよっぽど重い。また、私たちの大腸に棲む細菌たちの数は、約37兆個にも達する。さらに、著者が砂漠からとってきた微生物。培養すると、シャーレ全体で世界人口を超える個体数となる。
この、個々は顕微鏡サイズでありながらスケールがやたらとデカい微生物たちを追い求め、若き生物学者の著者は、世界の辺境へと飛び出してゆく。その行動範囲がまた、異様に広い。ラクダに揺られてサハラ砂漠を行くかと思えば、ホッキョクグマから身を守るためにライフル抱えて北極の氷河を登り、さらには砕氷艦に乗って南極へ……。
本書に通底するのは、知的好奇心と探究心。そして研究者としての実直さ。たとえば環境破壊後に生物調査をしても、それ以前のデータがなくては比較ができない。著者の「どこにどんな微生物がいるのかを調べておけば、それが過去と比較できる貴重な資料となる」という基礎研究を重んじる姿勢は、読んでいて好感度大、である。
ちなみにラクダで砂漠調査をしていた当時、著者の体重は100kgを優に超えていたそうだ。微生物を追い求めるのは体もビッグな研究者であった、という振れ幅も、今年読んだ本でいちばんだったこと間違いない。
峰尾 健一 今年最も「キーワード(と個人的反省)を感じさせられた」一冊
Facebookのデータ不正取得問題、GDPR(EU一般データ保護規則)の施行など、巨大プラットフォーム企業と個人情報についての話題が印象的な今年、「信頼」は大きなキーワードだったと思う。
オンライン空間がもたらす恩恵はなるべく維持しつつ、信頼も保てるようなシステムを構築できるのか。プライバシーの話以外でも、フェイクニュースの問題から金融の未来まで、さまざまなトピックにおいて信頼はカギになっている。 不信が強まれば強まるほど、信頼を築き上げた企業や個人へ支持が集中する流れも加速した。配車、宿泊、個人間の売り買いなど、信頼の問題を克服した(と多数が感じた)サービスの普及の速さは言うまでもない。
「錯覚資産」や「ブランド人」といったワードがビジネス書のベストセラーに顔を出し、個人レベルでの信頼についてもそのインパクトがますます意識されるようになった様が見て取れる。 信頼をめぐる潮流の変化を、正負両面バランスよく事例を出しながら整理してくれるのが本書『TRUST』だ。
良きにつけ悪しきにつけ、信頼は世の中を駆動させ、今はその動きの過渡期に差し掛かっていることがよくわかるだろう。信頼の行方を追っていけば、これからの時代が見えてくるはず。 ……なんて偉そうに書いてきたが、読みながら最も頭に浮かんだのは個人的な反省について。
気づけば今年は、自分史上最もレビューが少ない年になってしまった。着々と失われていくTRUST。へ、編集長…! 来年は盛り返していきます!
足立 真穂 今年最も「お勧めされた」一冊
認知症になったらどうしよう?
これは誰しもが持つ老いへの恐怖のひとつだと思う。かくいう私も、若年性アルツハイマーの映画を見たときは、「最近忘れっぽいかも」と慄いた。自分の身に起こらずとも家族ならどうだろうか。特に、加齢で加速度的に発症の確率が高まるのは自明の理、つまるところ老親がそうなることは大いにありえる。どうなっちゃうのだ? 面倒は見られるのか?
そんなところに、なぜか立て続けに周囲の友人や信頼する作家さんに勧められたのが、この本だ。『脳科学者の母が、認知症になる~記憶を失うと、その人は”その人”でなくなるのか~』。
タイトル通り、著者の恩蔵絢子さんは脳科学者だ。両親と同居をされているので日々世話をするのはそうなるのだとしても、専門的な知識が加わり、フラットに状況が書かれていくので読みやすい。それでいて娘としての気持ちの揺れ動きも伝わってくる。いや、そうだとしても、と。
介護の日々にさえ希望を見出す姿勢は、健気で、共感せずにはおられない。脳関係の本はあるようで、読むべきものは少ない。そんな中でお勧めされたので、私もお勧めすることにした。年末年始は家族との時間でもある。親の顔を見ながら、もしかしたら思い出しながら読むと、さらに実感のわく一冊になるだろう。
*
皆さま、2019年もHONZを、どうぞよろしくお願いいたします。