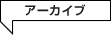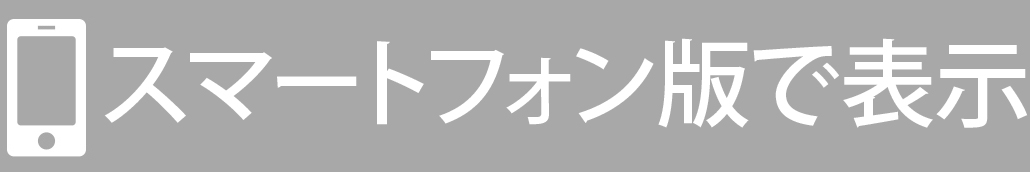教養・雑学
-
最新イギリス書店事情は『英国の本屋さんの間取り』で!
2024年7月14日2016年以降、イギリスで書店の数が増え続けているという。書店の減少が止まらなかった2010年頃から何がいったい変わったのだろう。コ…more
-
『定年後に読む不滅の名著200選』読書三昧の定年後はステキだぞ!
2024年7月2日本読みは人がどんな本を読んでいるかを気にする。同様に本好きは、自分が読んでいない名著が気になって仕方がない。おそらくHONZの読者も…more
-
温泉旅館のちょっとええ話、満載! 『宿帳が語る昭和100年 温泉で素顔を見せたあの人』
2024年6月27日「宿帳」である。旅館やホテルでの宿泊では記入が義務づけられているとはいえ、最近はネットで予約しがちなので、印刷されたものにサインする…more
-
『シャーロック・ホームズの護身術 バリツ 英国紳士がたしなむ幻の武術』その正体とは?
「明鏡止水 武のKAMIWAZA」というNHKの番組をご存知だろうか。格闘家でもある俳優の岡田准一が司会を務め、武道各流派を率いる一…more
-
『最強のコミュ力のつくりかた』コミュ力とは人としての魅力なのだ
皆さんはコミュ力に自信がおありだろうか?もしそれほど自信がないのであれば、本書の冒頭に記されている言葉はかなり衝撃的なはずだ。本書は…more
-
味の素営業マンの密着ルポ『地球行商人』がすごい!(本の雑誌2024年2月 綿入れ雪おろし号)
2024年5月5日外国人が日本を観光したいという大きな目的のひとつが「食」だという。一昔前のようにスシ、テンプラの時代は過ぎ去り、ラーメンや牛丼など、…more
-
『本屋のない人生なんて』本屋だからできることがある
近所に夜中まで開いている小さな本屋がある。開いているといっても、頑張って遅くまで営業しているという感じではない。店先に並べられた雑誌…more
-
あれから10年。『「笑っていいとも!」とその時代』が示す未来。
あれから10年です。 国民的人気番組だった『笑っていいとも!』が約32年間の歴史に幕を閉じた日から、きょう(2024年3月31日)で…more
-
『仲野教授の この座右の銘が効きまっせ!』は、笑って読めてタメになる最高の一冊だ!(← 自己肯定感マックスです)
2024年3月20日まいどお世話になっております、HONZレビュアーの仲野でございます。このたび、『仲野教授の この座右の銘が効く』という本を上梓いたし…more
-
社会学って何?と思うあなたに 『戦後日本の社会意識論 ある社会学的想像力の系譜』をどうぞ。
社会学者、と聞いて、誰をイメージするでしょうか? 古市憲寿さん、岸政彦さん、宮台真司さん・・・。 世代などによって、かなり異なるかも…more
-
最相葉月さんのエッセイ集『母の最終講義』、僭越ながらのレビューでござる
2024年2月27日う~ん、あかんがな。読み始めてすぐにそう思った。エッセイとは本来こういうものを言うのだろう。う~ん。なにがあかんか、まずはその話から…more
-
『The Tokyo Toilet』「PERFECT DAYS」が作る新しき聖地巡礼の旅
2023年も押し詰まった、ある日のあさイチの映画館。シネコンで一番広いスクリーンなのにほぼ満席だ。「PERFECT DAYS」が公開…more
-
論理にねじ伏せられていく快感『そこにある山 ー 人が一線を越えるとき』
2023年12月22日角幡唯介の名を初めて知ったのは二〇一〇年、『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』を読んだ時だった。心底驚いた。…more
-
「どんな本を読むべきか」と問う人の深刻な問題『人生を変える読書』
2023年12月17日私が当惑する「ある質問」 「どんな本を読めばよいですか?」 講演会やセミナーなどで、ビジネスパーソンや学生など、さまざまな方とお会い…more