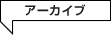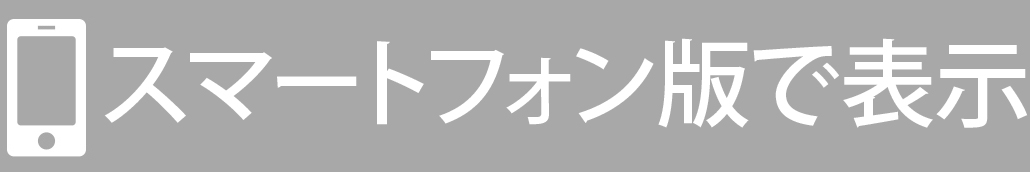医学・心理学
-
『僕とぼく 妹の命が奪われた「あの日」から』 「佐世保小6殺害事件」被害者の兄ふたりの“その後”
"2004年6月、長崎県佐世保市の小学校で6年生の女子児童が同級生の女児にカッターナイフで喉を切られ死亡する事件が発生した。学校内で…more
-
「『こわいもの知らずの病理学講義』につまずいた人、必読!」ってどういう意味やねん! 『おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわかりやすいがんの話』
2019年7月7日おしゃべりなおばちゃん病理医による「がんの図鑑」。著者自らのイラストを駆使しながら、がんとはどういう病気か、が、わかりやすく解説され…more
-
『ストーカーとの七〇〇日戦争』ストーカーは病気である!
本書は被害当事者が、ストーカー行為の一部始終を赤裸々に語った数少ない本である。一度は信頼した人が変貌していく過程に総毛だつ。more
-
『「うつ」は炎症で起きる』 「それは体の問題」という新たな視点
若い医師はあるとき、リウマチ性関節炎と診断されていた女性患者がうつ病をも患っていることに気づいた。そのささやかな発見に気をよくした彼…more
-
『Dr. ヤンデルの病院選びーヤムリエの作法』を読んで病院選びの達人をめざそう
2019年6月8日あのDr.ヤンデルの本である。と言われても「?」の人が多いかもしれない。ツイッターのフォロワー数10万人近く、間違いなく日本でいちば…more
-
『世にも危険な医療の世界史』を買ったのは、どういう人たちなのか?
2019年5月30日"発売した瞬間にHONZメンバーがどよめく、というか「おおっ!」と沸くことが最近頻発しています。面白いノンフィクションが次々と世に送…more
-
読めば気分が…、医学譚全61話 『爆発する歯、鼻から尿―奇妙でぞっとする医療の実話集』
2019年5月27日珍書というべきか奇書というべきか、何しろ驚愕の一冊である。『鼻から尿』?、それに『爆発する歯』?そんなことあるはずないやろ!という…more
-
衝撃! ”生命科学クライシス-新薬開発の危ない現場”
2019年4月27日「なんとかの危機」的な本はけっこう多い。執筆は専門家ではなくてジャーナリストだし、「煽り系」の本がまた出たかと思って読み始めた。しか…more
-
何でも治ることを売りにした最悪の治療法の歴史──『世にも危険な医療の世界史』
2019年4月25日現代でもインチキ医療、危険な医療はいくらでも見つけることができるが、過去の医療の多くは現代の比ではなくに危険で、同時に無理解の上に成…more
-
日本医学の大恩人になりかけた男『ウイリアム・ウイリス伝』
明治政府は、薩摩藩と関わりの深かった英国人医師ウイリアム・ウイリスを軸にして、日本に英国流の医学を導入しようとする。しかし、最後の最…more
-
『わたしが「軽さ」を取り戻すまで シャルリ・エブドを生き残って』死を免れた女性漫画家の“その後”
2015年1月7日11時30分、フランスのパリ11区にある風刺新聞社「シャルリ・エブド」に武装した覆面男2人が侵入し、編集会議中の社…more
-
身近なれど未知なる障害『吃音 伝えられないもどかしさ』
2019年3月28日魂の一冊である。『吃音 伝えられないもどかしさ』は、自らも吃音に悩んだ近藤雄生が80人以上の吃音者と対話し、その現実に迫る渾身(こん…more
-
『生命科学クライシス─新薬開発の危ない現場』着実に進むために、急がば回れ
本書は「再現性」の問題に焦点を当てながら「科学が正道を踏み外すさまざまなパターン」について迫る1冊だ。生命科学の歩みは決して止まって…more
-
『クリエイティブ・ラーニング 創造社会の学びと教育』学ぶことの遠い将来を見定める
学びや教育を題材にした書籍に多いパターンは、起こっている問題を分析した後に、あるべき姿や改革案を提案する本である。しかし、本書はその…more
-
『吃音 伝えられないもどかしさ』吃音者の著者が当事者たちの現実に迫る
本書では、重度の吃音者で、そのことを苦に自殺未遂まで起こした高橋啓太という男性の回復への過程を下敷きに、自らも吃音者であった言語聴覚…more